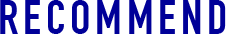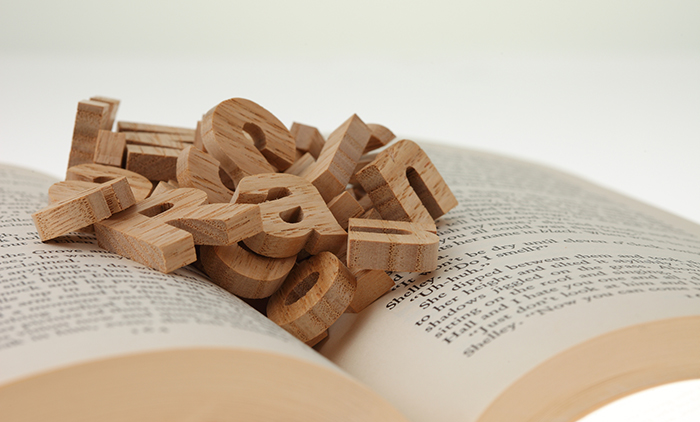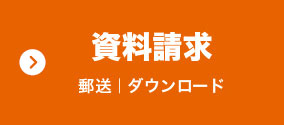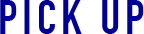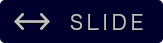英検®5・4・3・準2級・2・準1級・1級のリスニング対策、コツまとめ!

英検では、どの級でもリスニング問題が課されます。受験級によって放送される回数が変わったり、設問数が異なります。今回は受験級ごとのリスニングテストの詳細と解答のコツをご紹介します。ぜひご参考ください。
45年の実績!
英会話・資格対策・留学準備の日米英語学院
目次
英検®5・4・3級のリスニング対策とコツ

■英検®5級のリスニング対策
5級ではリスニングテストは一次試験の後半で行われます。家族、友達、学校、趣味、旅行、買い物、スポーツ、映画、音楽、食事、天気など、身近な話題が出題されます。約22分で25問出されます。およその合格ラインは6割程度です。普段から試験時間と同じだけ英語を聞く練習をしておけば、本番で力尽きてしまうことも少なくなるでしょう。5級を受験されるのは小学生の方が多いので、集中力を鍛える意味でも実戦形式で過去問や予想問題にチャレンジしましょう。どの大問でも英文・選択肢は2回読まれますので、焦らずに落ち着くことが大切です。片仮名読みをせず、聞こえてきたままの音を繰り返す音読練習をし、声に出すことでリスニング力を鍛えましょう。
第1部は全10問で、イラストを参考に対話と応答を聞き、適切な応答を答えます。選択肢は印刷されていないので注意しましょう。疑問文(what、where、when、why、how)が主体になりますので、疑問詞の意味をしっかり理解し、何度も聴いて耳を慣らしておきましょう。
第2部は5問で、会話文を聞き、その内容についての答えを選びます。問題用紙には選択肢の文章が書かれています。音と単語がしっかり一致するように練習しましょう。こちらも疑問詞が主体になりますので、それぞれの疑問詞の違いをしっかり覚えましょう。
第3部は10問で、短い英文を3つ聞いて、イラストの内容に合うものを選びます。問題用紙にはイラストのみ印刷されています。挨拶や命令などのきまった表現が問われることが多いので、特徴をしっかり押さえておくと良いでしょう。
■英検®4級のリスニング対策
4級のリスニングテストは5級であった話題に加え、自己紹介や道案内、海外の文化などに関する話題が出題されます。試験時間は30分、問題数も30問と増えます。どの部でも問題文は2回読まれますが、5級に比べるとスピードが少し上がり、一度に聞く量も増えます。キーワードになりやすいのは数字や名詞などです。聞きながらメモを取る練習も一緒に行うとよいでしょう。聞こえてきたそのままをメモするのではなく、数字が聞こえてきたら数字だけをメモに残す、と言う訓練をしましょう。およその合格目安は6割正解です。
第1部では男女二人の会話文を聞き、最後の発話にふさわしい解答を選びます。全部で10問です。問題用紙にはイラストが描かれていますので、参考にしましょう。読みあげられる文章は印刷されていません。友人同士、親子、店員と客など、普段からよく聞くような内容から出題されます。問題文の最後に話した人が文頭の疑問詞で何と言ったかをしっかり聞く練習をしましょう。
第2部では第1部同様、男女の会話を聞きます。2部ではその内容と一致するものを選びます。全部で10問です。選択肢は印刷されていますので、違うところはどこかを確認し聞きながら下線やバツ印などを書き込んでメモをしましょう。1回目の放送で解答ができた場合は、次の問題の選択肢を先読みしてどこを聞けばいいのかを確認しましょう。
第3部は会話文ではなく、英文を聞いてその内容と一致するものを選びます。英文は25語程度、時間にして約15秒話されます。2部同様選択肢は印刷されていますので、メモと先読みを活用して解答していきましょう。
■英検®3級のリスニング対策
3級のレベルは中学卒業程度のレベルとされ、身近なことに関する内容を理解することができるかが問われます。試験時間は約25分で、合計30問に答えます。第1部では1度しか放送されませんので、よりしっかりと聞く必要があります。
第1部では2人の会話文と選択肢3つが読みあげられます。問題用紙には参考にするイラストが描かれていますので、それをヒントにしっかりと聞いて設問に答えましょう。最後に話した人の文頭に疑問詞が来ることが多いので、何と言ったか気を付けて聞きましょう。全部で10問に解答します。
第2部では会話文を聞き、その内容について質問されますので正しい解答を選びましょう。2部も全10問です。問題用紙には選択肢が印刷されています。会話文・質問文共に2度放送されます。質問の多くは時間や場所を答えたり、登場人物のうち誰であるとか、何をしたというようなことを選択する問題が多いです。「彼らは何について話していますか」という、会話全体の状況や内容について尋ねられることもあります。
第3部では35語程度の短い文章を聞き、その内容についての質問がされます。問題用紙に選択肢が印刷されていますので、4つのうち正しいものを選択します。問題は全部で10問です。文章はある人物のエピソードであることが多く、主語がIの場合や特定の人物であることが多いです。公共の場のアナウンス問題も出題されます。最初の1文をしっかり聞き、どんな状況の文章なのかを理解しましょう。2部同様、英文は2回読まれますので、1度目にしっかり解答ができたら次の問題の先読みに充てましょう。選択肢のどこが違うのかを確認し、実際に聞くときはそこに注意して聞くようにしましょう。例えば時間が書いてあれば、時間に流れを意識して聞くようにしたり、動詞が書いてある場合は何をするのかに注意して聞く、などです。また先読みをしている間は次の問題に移るタイミングを聞き逃さないように注意しましょう。
英検®準2級のリスニング対策とコツ

■英検®準2級リスニングの試験問題
準2級は高校中級程度のレベルとされ、リスニングでは日常生活の話題に関する内容を理解できるかが問われます。試験時間は約25分で、30問に答えます。準2級からは全て放送回数が1回になるので、一度でしっかり聞けるようになる必要があります。合格の目安は65%正解です。
第1部、第2部では会話文が放送されます。第3部では物語文や説明文が放送されます。それぞれ学校や家庭、職場や公共施設、店舗での会話や電話、アナウンスと言った場面で、趣味、旅行、学校、買い物、スポーツなど、生活中に耳にするような身近な内容の話題が多く取り扱われます。それぞれ問題数は10問出題されます。
■英検®準2級リスニングのコツ
リスニングテストの開始冒頭と2部・3部の冒頭には「このように解答しましょう」という指示文が放送されますので、この時間を利用して2部・3部の先読みをしましょう。この際、「では、始めます」の音声を聞き逃さないように注意しましょう。
第1部では問題となる会話文も選択肢も全て放送されますので、先読みができません。会話の流れをしっかり聞いて、どんな関係の人の会話なのか、最後に話した人は何を尋ねたのかを押さえましょう。とくに最後の話者の話し始めを聞き逃さないように注意します。早く選択できた時は第2部の選択肢を先読みする時間に充て、「Number…」という問題番号を読む音声が聞こえたらまた聞くことに集中する練習をしましょう。
第2部では選択肢から問題文を推察しましょう。例えば4つの選択肢全てに動詞が含まれている場合は、登場人物はどんな行動を起こすのかが問われるでしょう。選択肢の主語が同じ場合は、その人がどのような行動をするのかを注意して聞きます。先読みができた場合は、選択肢の中で異なる部分に下線を引くなどしてチェックをし、聞きながら○×をつけるようなメモを取ると、設問に対する解答を探しやすくなります。
第3部では何について話されているのかがすぐに判断できるようになりましょう。架空の人物についてのお話、公共の場でのアナウンス、社会的・文化的・科学的トピックの3パターンが多く出題されます。最初の文章で主題が述べられることが多いので、先読みに集中してしまい聞き逃してしまった、と言うようなことがないように気をつけましょう。
■英検®準2級リスニングの対策と勉強法
準2級では出題形式や内容が近しい場合が多いので、過去問や模擬問題をたくさん解いて問題のパターンを理解しておくことが大切です。3級まで学習してきた人は、放送回数が1回になり、しゃべるスピードも上がってくるので焦ってしまうかもしれません。しかし、どんな問題パターンかを推察できるようになれば、何が聞かれるかを選択肢とともに予測することができるようになってきますので、できるようになるまでたくさんの問題をこなしましょう。
また話すスピードが速くなることで、英語特有の「音声変化」が生まれます。「Good Afternoon」などは「グダフタヌーン」と聞こえるようにdとaがくっついて聞こえたり、「I want to…」のようにtが重なる場合は、「アイウォントトゥ」と最初のtを発音せずに、「アイウォントゥ」と欠落して聞こえるようになります。英語にはこのようなルールがいくつかありますので、答え合わせをする際には放送文を聞きながら文字でも読み、「この音は変化するのだな」「この音は言わなくなるのだな」ということも合わせて確認していきましょう。音とスペルが一致して聞こえるようになるまで、何度も聞きましょう。
実際に声に出して読むことも効果的です。大きな声で、イントネーションなどもしっかり真似ておなじくらいのスピードで読めるように訓練しましょう。声に出せない音は聞き取りもしにくいと言われます。難しい場合は再生スピードを落としてゆっくり丁寧に発音し、徐々に放送文と同じスピードでしゃべられるようになるまで繰り返し音読しましょう。
準2級のリスニング問題について更に詳しく解説した記事がこちらになります。ぜひご覧ください。
英検®2級のリスニング対策とコツ

■英検®2級リスニングの試験問題
2級は高校卒表程度のレベルとされ、リスニング問題では社会性のある内容を理解することができるかが問われます。試験時間は約25分で、30問に答えます。6~7割の正答率を目指しましょう。放送回数は1回です。
試験は第1部、第2部に分かれ、各15問ずつ出題されます。学校・家庭・職場・店舗や公共施設、電話やアナウンスといった場面で、趣味、買い物、道案内と言った生活に身近な話題から、歴史、教育、自然環境、テクノロジーについてなど、ニュースで聞くような話題まで取り扱われます。
■英検®2級リスニングのコツ
リスニングテストの冒頭では指示文が放送されます。これはどのように解答するかの説明になりますので、過去問なので実践的に問題を解いたことのある方は聞き流して頂いても問題ないでしょう。この時間に印刷されている選択肢を「先読み」します。
先読みする際は、選択肢の中で同じ部分と異なる部分に着目します。例えば全て同じ主語の場合は、その主語になっている人物がどう行動するかに注意して放送を聞きます。「company」「manager」「office」などの選択肢が並んでいる場合は、舞台は職場であることが推察できます。このように、選択肢を読んでどんなことが聞かれるか放送文を推測しながら先読みをしましょう。先読みに集中しすぎて「では始めましょう」「Number…」といった、本番が始まるサインを聞き逃さないように注意しましょう。
上手く放送文が聞き取れなかった場合には注意が必要です。どうしても「あの音は何て意味だっけ…?」と考えてしまい、選択肢を決めかねる問題も出てくるでしょう。次の問題が放送されるまで10秒のポーズがありますので、放送終了後はその時間で選択肢をマークし、次の問題に集中する必要があります。もう一度聴きなおすことはできないので、分からなかった場合は聞こえた単語の選択肢をマークし、次の問題の先読みに進んでしまいましょう。立て直しができるかが残りの問題の正答率を上げるカギになります。1問にとらわれすぎない訓練をしましょう。
■英検®2級リスニングの対策と勉強法
2級のリスニングは出題形式がほぼ決まっていますので、過去問や予想問題などを繰り返し演習しましょう。問題は一度解いて、答え合わせをして、終わり、ではいけません。正解するまで何度も音声を聞きましょう。
正解した問題でも放送文を書きとる「ディクテーション」に活用したり、放送文と同じようにしゃべる訓練をする「オーバーラッピング」や「シャドーイング」に活用しましょう。
「ディクテーション」は、聞こえてきた音声を書きとる訓練です。放送中は曖昧にしか聞こえなかったけど選択肢は選べた、と言う場合はディクテーションを行い、どの部分があいまいに聞こえてしまったのかを把握しておきましょう。早い音で話される英文の場合、脱落や連結などの「音声変化」が起こることがあります。この音声変化がどのようなときに起きるのか、音とスペルを一致させるのに適した訓練がディクテーションです。音声変化を理解し、脳内で素早く英文を構成する練習になります。書きとるのでしっかり聞く練習になったり、集中力を高めたりする練習になります。
ディクテーションが難しい場合は「オーバーラッピング」から練習をしましょう。「オーバーラッピング」はスクリプトを読みながら、音声と同時に自分でも発話する練習方法です。文字と音を一致させる練習になりますし、聞くだけでなく話すことも同時に行うことで記憶の定着率が上がります。発音やイントネーションに注意し、できる限り真似しましょう。早すぎて口がついていかない場合は再生速度を落としましょう。あいまいなまま速いスピードで発声するよりも、ゆっくりでも正しく発音することを目指します。同じ文章で何度も繰り返し、自然なスピードで発音できる様になったら、次は「シャドーイング」を目指しましょう。
「シャド―イング」は、スクリプトを見ずにお手本の音声を影のように追って発話する訓練です。文字を読まなくなるだけでこんなに難しくなるのか…、と感じてしまう人も多いでしょう。シャドーイングは通訳を目指す方も行っているトレーニングなので、とても難易度の高い学習方法です。はじめはスクリプトを見ながら、慣れてきたらどんどん文字から目を話して、音声に集中して発話していきましょう。こちらも難しい場合は再生速度を下げたり、またオーバーラッピングに戻ったりして、自然に行えるようになるまで何度も繰り返しましょう。
2級のリスニング対策についてはこちらの記事でもご紹介しています。実際の問題例などを挙げて解説していますので、合わせてご確認ください。
英検®準1級のリスニング対策とコツ

■英検®準1級リスニングの試験問題
準1級は大学中級程度のレベルとされ、出題範囲は家庭・学校・職場・店舗や公共施設、アナウンスや講義内容などの場面で、社会生活一般のことやテクノロジー、ビジネス、政治の話題など多岐にわたる話題が主題となります。試験時間は約30分で、合計問題数は29問です。Part1、Part2では12問ずつ、Part3では5問出題されます。合格のためには7割取得を目指しましょう。
■英検®準1級リスニングのコツ
リスニング問題が開始される説明は日本語で放送されますが、以降続けて流れる各パートの問題概要からは全て英文で放送されます。とはいえ、放送される内容は毎回同じですので、放送時間は先読みに充て、「Now, we will begin…」の音声に合わせてリスニングに戻り、集中する癖をつけましょう。
Part1は会話形式の音声を聞き、質問に沿った選択肢を選びます。やり取りをする人の発言の回数は増え、しかも固定されていません。少なくても4回、多いと7回ほどの会話のやり取りを聞きます。そのため「そろそろ終わるかな?」などと考えてしまい、集中力が途切れてしまいがちです。選択肢の英文自体の難易度はそこまで高くないので、しっかりと聞き、質問文が終わると同時に解答して先読みを行えるように何度も練習しましょう。
Part2はナレーションを聞き、内容に関する質問2問に答える問題です。1つのナレーションにつき2問答え、合計6つのナレーションを聞き、12問に答えます。ナレーションと問題文が放送されますので、問題用紙に印刷されている選択肢から適切なものを選びましょう。Part1同様に、選択肢の先読みをしておくとよいでしょう。ナレーションは新しい技術や歴史上の話、動物の生態など多岐にわたります。普段から様々な英文を聞いて対策をしていないと、いったい何の話をしているのだろう、となってしまいます。ニュースサイトなどを活用して色々な情報に触れておきましょう。
Part3では日常生活で体験する放送、CM、音声ガイダンスなど「Real-Life形式」と言われる
放送を聞き、質問に答えていきます。5つの文章が読まれ、それぞれに1問ずつ、合計5問に解答します。Part1、Part2と異なり、問題冊子に印刷されているSituationと問題文、選択肢を読む時間が放送前に10秒間与えられます。すべてに目を通すには時間が足りないかと思いますので、問題文を中心に読み、何を聞くべきかを理解して音声を聞きましょう。
読まれる文章をメモしたり、選択肢にマルやバツをつけて情報を整理しましょう。準1級では言い換えも行われますので注意が必要です。
■英検®準1級リスニングの対策と勉強法
まずは公式サイトで過去問を確認し、全問正解できるようになるまで何度も解きましょう。その際、スクリプトを見ながら「オーバーラッピング」で音読したり、慣れてきたら「シャドーイング」を行って自分でも実際に発話してみましょう。
まずはオーバーラッピングを行い、スペリングと音を一致させましょう。はじめは日本語を考えることを意識せず、音に集中します。イントネーションやスピードを意識し、同じ速度で読みあげられるように何度も繰り返しましょう。イントネーションや音が正確に発話できるようになったら、シャドーイングにもチャレンジしてみましょう。スクリプトがなくなると途端に難しくなってしまいますので、慣れるまではスクリプトを見ながら行い、徐々に文字を見ずに追いかけられるように練習しましょう。音に慣れたら日本語の意味も意識しつつ読みましょう。
「ディクテーション」を行うのも効果的です。ディクテーションは音を聞き、その英文を文字起こしするトレーニングです。はじめは音声の再生速度を落として行ったり、聞きとれたところまで書く→聞き取れなかったところに戻り、また書くなど繰り返し音声を再生しましょう。こちらの作業を行うと音と文字が一致しやすくなります。集中して聞き、あいまいな部分を無くすトレーニングになります。
準1級リスニングのスピードは速いですが、慣れてきたら少しずつ再生スピードをさらに上げて耳を慣らしていきましょう。早いスピードに慣れてしまうと、実際の試験の時のスピードがゆっくりと感じられます。
過去問を周回し終えたら、英語のニュースなどから様々な音声を聞く練習をしましょう。なるべく英語を聞かない日を作らないように、毎日少しずつでもいいので英語を聞き、耳を慣らしていきましょう。
準1級の対策についてはこちらの記事でその他の技能対策を合わせて学習方法をご紹介しています。ぜひご確認ください。
英検®1級のリスニング対策とコツ

■英検®1級リスニングの試験問題
1級は大学上級程度のレベルとされ、英検の中で最も難しい試験です。出題範囲は家庭・学校・職場・地域など社会生活の場面・話題から出題され、内容は時事問題から歴史・文化、自然科学、ビジネスなど多岐にわたります。試験時間は約35分で、問題数は27問です。
会話の内容に関する質問に答えるPart1が10問、文章の内容に関する質問に答えるPart2が10問、Real-Life形式の内容に答えるPart3が5問、インタビューの内容に関する質問に答えるPart4が2問あります。
■英検®1級リスニングのコツ
冒頭の音声確認以外、全て英語で話されます。Partごとの解説も注意文も全て英語で読まれます。とはいえ、過去問などで対策を行っていれば毎回同じ文章を読まれますので、この時間は先読みに充てましょう。
全てのPartで共通して言えることは、解答を先読みすることです。可能ならば前半の筆記試験を早めに終わらせ、問題文や選択肢を先読みする時間に充てましょう。これができるようになると、リスニングの解答時間を先読みにあてるだけの場合に比べ、解答がぐっと楽になります。10~15分取れるようになるのが理想ですが、筆記試験も難しいので少しずつ解答スピードを上げて先読みの時間を取れるように練習しましょう。1級の問題ではリスニング問題の解答時間を使っての先読みは難しく、時間いっぱい使って問題を解くことも多いので、できれば筆記の時間をリスニングの先読みに充てられるように工夫しましょう。また、リスニングは集中力が途切れて聞き逃してしまうと、後からどんなに考えても答えを出せる確率は上がりません。そのため、このような場合は聞き取れなかった問題はあきらめて次の問題の先読みに充て、必ず正解させる心づもりで臨みましょう。
Part1の会話の内容問題では解答を先読みし、その文から何に注目すれば良いかを把握して問題を聞くように心がけましょう。例えば選択肢の主語がすべてSheで始まっていた場合は、会話文の登場人物の女性の声により注意して聞きます。動詞が異なっている場合はどんな行動をするのかを意識しましょう。会話の内容が専門的で意味の分からない単語が読まれても、前後の文章から単語の意味を推察できるように練習をしておきましょう。
Part2の文の内容一致問題では長い文章が読まれます。また内容も論説的・学術的なものが多いので、分からない単語が出てくる機会も多いでしょう。1つの読み物に対して2問解答する形式の問題が5題読まれますので、求められる集中力も高いレベルになります。タイトルと最初の一文をしっかり聞くことを意識すると、これから何の話がされるのかが分かりますので、その後のリスニングの心構えになります。特に意識して聞きましょう。
Part3のReal-Life形式の問題ではSituationを読む時間が与えられていますので、何について話されるのかの推測が他の問題よりもしやすいです。Questionの読みあげを聞き逃さないように注意しましょう。
Part4のインタビューの内容について答える質問では最も長く聞き取りをする必要があります。しかし問題数は2問ですので、解答に必要のない部分も聞く必要があります。Part4の問題解説の英文が読まれている間に選択肢にさっと目を通しましょう。これができると、解答の選択肢内に出てくるキーワード前後の音声が流れてきたときに集中して聞くことができるようになります。一方で、インタビューの冒頭では、何についてのインタビューが入りますので、この部分はしっかりと聞き、これから何の話が行われるのかをしっかりと理解しておりましょう。そのため、選択肢の先読みはあまり深追いせず、さっと目を通す程度に留めましょう。
■英検®1級リスニングの対策と勉強法
まずは問題文や解答の選択肢を先読みする練習をしましょう。先読みができるようになると、放送される内容に対しての事前準備ができますので、心構えができます。過去問や練習問題で自分が先読みに必要な時間を覚えて、なるべく前の問題を引きずらないように先読みをする練習をしましょう。
また、毎日英文を耳に入れることを意識しましょう。どんなに時間が無くても必ず毎日、何かしら英語の音声を耳に入れましょう。Part1が苦手な方は会話文を、Part2が苦手な方はニュースなどのある程度文量のある音声を聞くなど、できるだけ毎日繰り返しましょう。
リスニング中に大意はつかめるのに肝心の問題文は何と言ったか覚えていない、と言う場合は、メモの取り方を工夫してみましょう。すべての単語は書きとれません。そのため、どの言葉をメモに残すかが大切になります。主題・目的、インタビュアーの質問に対する解答などからまずはメモを残すようにしましょう。慣れてきたら、選択肢のキーワードのパラフレーズとなり得る単語が聞こえたらメモに残す、などを意識しましょう。
1級のリスニング対策については、こちらの記事でも詳しく解説しております。ぜひご参考ください。
塾やスクールの活用も視野に!

いかがでしたか?今回は、英検のリスニング対策について、級別に詳しくお伝えしました。過去問や練習問題をしっかりと反復し学習すれば、英検のリスニング問題を攻略することは可能です。どうしても苦手意識が払しょくされない、学習方法があっているのか分からない、なかなか点数が取れない、効率的に学習したい…と言う場合には、スクールや塾に通い、専門の講師からテクニックやコツを学ぶことも検討されてはいかがでしょうか。
塾やスクールに通うと、このようなメリットがあります。
・自分の気づかなかった弱点を客観的に知ることができる
・分からないことを聞ける先生がいる
・同じ目標に向かう仲間ができ、モチベーションが維持できる
・効率よく学習できる
一般的な学習塾やスクールの場合、英検●級を取得したい方向けに、すでにカリキュラムが組まれていることが多いです。リーディングは自力で学習できるのにな…と思っても、カリキュラムが決まっているスクールの場合はリスニングの授業だけ受ける、と言うことは難しいこともあります。
また、上位級になると対策を行っている塾やスクールも数が減ります。なかなか思い通りのレッスンを見つけられない、と言う方も多いのではないでしょうか。
日米英語学院では、級別対策に加え技能別対策も行えます。それは、プロのコーディネーターが受講される方に必要なレッスンを「個人別カリキュラム」として作成し、必要な技能だけを効率よく学ぶ道筋を作成してくれるためです。
英検のリスニングに特化したクラスのみを受講することも可能です。もちろん、他の技能と合わせて学習したり、資格対策に加え日常英会話の学習も行ったりなども可能です。その人の英語の学習に必要なカリキュラムをプロのコーディネーターが作成します。
レッスンは通学/オンライン、グループ/プライベート、日本人講師/外国人講師から選択が可能です。また、講師は英検1級取得やTOEIC900点取得などの厳しい審査を経た講師ばかりです。英検リスニング対策に特化した先生もいらっしゃいますので、効率よく学習を進めることができます。
聞き取れるまで何度も繰り返しました

- お名前
- A.K.さん
- 職業
- 高校生
- 受講クラス
- リスニングクラス、リーディングクラス、面接対策クラス
リスニングのプライベートレッスンでは聞き取れるまで何度も繰り返し、特に聞きづらい部分では「聞き取るコツ」を教えてもらいました。レッスン中に何度も言われた「話すことのできないものは聞くこともできない」という言葉が印象的でした。
ご自身が今どんなレベルなのか、これまでどんな学習を行ってきて、どんな悩みを持たれているのか、いつまでにどのくらいのスキルを習得したいかなど、それぞれの状況によって習得までのアプローチは異なります。まずは対面/オンラインの選択が可能な無料の学校説明会にてお話をお聞かせください。通学までは考えていなくても、情報が手に入ります。リスニングを得意スキルにするために、まずは一度ご相談ください。
45年の実績!
英会話・資格対策・留学準備の日米英語学院